きのこを食べて、消化されないまま便に混ざっていたことはありませんか。
きのこが消化されないことの理由は、「胃腸が弱っている」「大量に食べた」「しっかり噛(か)んでいない」の3つですよ!
不溶性食物繊維が豊富なきのこは消化されにくく、そのまま出てくることがあるのです。
 おもち
おもち消化されないまま出てきて驚いたことがあるよ!
食べ方によっては便を増やして腸内を汚してしまい、胃腸へ負担をかけることがあります。
この記事では、「きのこが消化されない理由」や「きのこの栄養素」、「消化しやすくなる調理法」について解説します。
きのこを食べたいが、食べると便が出にくくなる方、胃腸の調子が悪くなる方は参考にしてくださいね。
きのこが消化されない!そのまま出てくる3つの理由


不溶性食物繊維が豊富なきのこを食べると、消化されないまま出てくる理由は3つあります。それでは詳しく解説していきますね。
- きのこを胃腸が弱っているときに食べた
- きのこを大量に食べた
- きのこをしっかり噛(か)んで食べていない
きのこを胃腸が弱っているときに食べた
胃腸は私たちの体に必要な栄養を取り込むために、毎日休まず働いています。
不眠や体調不良、ストレスからの暴飲暴食、クリスマスや年末年始など食べる機会が増えると、ますます胃腸が休まる暇がなくなり、消化力が弱まってしまいますよ。
そのようなときに、不溶性食物繊維が豊富なきのこを食べると、消化されないまま出てきたり、下痢になったりする場合があるようです。
ところで、あなたは食べ物の消化にかかる時間をご存じですか。
| 消化にかかる時間目安 | |
| 胃 | 通常の食事は平均2~3時間、揚げ物やお肉は平均4~5時間かけて胃液と混ぜ糊(のり)状にする。 |
| 小腸 | 胃で消化されたものを平均5~8時間かけて吸収する。ここで水と栄養の80%が吸収される。 |
| 大腸 | 平均15~20時間かけて、食べ物のカス(食物繊維)を便として固形化する。 |
上記の表を見ると消化に時間がかかることがわかりますね。胃腸が元気なときにきのこを美味しく食べましょう!
きのこを大量に食べた
和食・洋食・中華など、どの料理にも使いやすいきのこですが、大量に食べると消化されずに胸やけをする場合があるようです。
一日に食べる目安は、「50g~100g」程度といわれています。
- えのきだけ・・・1袋
- しめじ・・・・・1パック
- しいたけ・・・・5~6個
- エリンギ・・・・大1個
火を通すと生の状態よりも量が減るので、つい食べ過ぎてしまいますよね。1日の適量を参考にして美味しく食べましょう。
体重や体調、目的により適切な摂取量は異なりますので、ご自身の体に合った量に調整してください。
きのこをしっかり噛(か)んで食べていない
きのこは不溶性食物繊維が豊富なので歯ごたえがあり、消化しやすくするためにはしっかりと噛(か)むことが大切です。
体調がよく、きのこを食べ過ぎていないのに、きのこが消化されないまま出てくる理由は、噛(か)む回数が少ないのかもしれません。
よく噛(か)むことが健康によいとされる理由は下記のとおりです。
- よく噛(か)むことできのこが小さく砕かれて胃腸への負担が軽減する
- よく噛(か)むことで唾液の分泌が多くなり、虫歯予防になる
- よく噛(か)むことで血糖値の上昇を緩やかにしてくれる
このように、ゆっくりしっかりと噛(か)むことで胃腸への負担を減らし消化が促されるだけでなく、歯の健康や肥満防止にもつながります。
きのこだけでなく、食事はよく噛(か)んで食べましょう。
きのこが消化されない状態でも栄養素は吸収できる!


不溶性食物繊維が豊富で消化しにくいきのこですが、消化されないまま出てきたら、食べても栄養素が吸収されているか気になりませんか。
実は、きのこが消化されないまま出てきても、栄養素は吸収されるそうです。その理由について解説しますね。
栄養素が吸収される理由
きのこの成分に含まれる主な栄養素のビタミンB群は、その水に溶けやすい性質があります。
そのため、調理によってきのこの旨味や栄養素が料理に溶けだしているので、きのこが消化されずに出てきても、食べることで栄養素を吸収することができますよ。
ところで、みなさんはきのこに含まれる栄養素をご存じですか。ビタミンB群以外にも、私たちの体を整えるのに必要な栄養素を含んでいます。
きのこをより知るために、含まれる主な栄養素について調べました。
きのこに含まれる主な栄養素
きのこに含まれる主な栄養素は、4種類あるので、1つずつご紹介していきますね。
食物繊維
- 腸内環境を整える不溶性食物繊維が多い
- 便の量が少ない時に食べると便の量を増やす
- 便が固い時に食べると、便の量が増えすぎて、より便秘になる可能性がある
便が固い時はきのこのなかでも、水溶性食物繊維が多く、便を柔らかくしてくれるえのきやなめこを食べるのがおすすめです。
ビタミンD
- カルシウムの吸収を促す働きがあり、骨や歯を丈夫にしてくれる
- 乳製品と一緒に食べるとカルシウムの吸収アップが期待される
- 免疫力アップに欠かせないエルゴステロールという物質が豊富
のちほど、きのこと乳製品を使った「アレンジ料理」をご紹介しますので、最後までお読みくださいね。
ビタミンB群
- 8種類のビタミンの総称
- ビタミンB1、B2、B6、B12、葉酸、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸が豊富
- 疲労回復や美肌効果が期待される
水に溶けやすいので、料理の汁も残さず食べると無駄なく栄養素を取り込めますよ。
B-グルカン
- 免疫細胞の活動を活発にし、免疫力アップ効果が期待される
- コレステロールを下げる
- アレルギー改善の効果もあるとされる
B-グルカンが特に多いのは、まいたけやぶなしめじです。スーパーで手に入るので取り入れやすいですね。
このように豊富な栄養素を含むきのこを、せっかくなら消化されやすい料理で食べたいと思いませんか。少しの工夫で、きのこの栄養素を摂取しやすくなる調理法をご紹介します。
きのこが消化されないことを防ぐ胃腸を守る調理方法!


きのこを食べるときに、「よく噛(か)むのがよい」とわかっていても、毎回消化しやすくなるまで噛(か)み続けるのは難しいですよね。
そこで、きのこ料理を作るときに、「消化しやすい+栄養も吸収しやすくなる」調理のコツをお伝えします。
斜め薄切りにする
きのこを消化しやすくするには、きのこの繊維を断ち切ることがポイントです。
パックから出し、ほぐしてそのまま調理しがちですが、繊維を断ち切るように斜め薄切りにすると、消化しやすくなり胃腸への負担を減らすことができます。
みじん切りにする
きのこに含まれるビタミンB1は水溶性なので、みじん切りするとより溶けだしやすくなります。
みじん切りにすることで量が増えるので、肉団子やハンバーグに混ぜるとひき肉の量を減らすことができ、ヘルシーな料理に仕上げられますよ。
きのこの食感が苦手な子どもも、みじん切りにすると気づかないうちに食べてしまいます。
ペースト状にする
小さな子どもや高齢者できのこを噛(か)むことが難しい場合は、ペースト状にして食べましょう。ペースト状にすると食べやすくなるだけでなく、料理の幅が広がりますよ。
きのこペーストを作り置きし、鶏肉にペーストとチーズをのせて焼いたり、フランスパンにのせてカナッペ風にしたりすると、白ワイン・日本酒に合うおつまみになります。



簡単に作れるきのこレシピを紹介するよ♪
きのこペーストの作り方
材料
- 好きなきのこ:(250gから300g)
- ニンニク:2片~3片
- オリーブオイル:大さじ2
- 塩・ブラックペッパー:適量
- 唐辛子:お好みで
作り方
- きのこの石づきを取り、食べやすい大きさに切る(加熱後フードプロセッサーでペースト状にする)
- つぶしたニンニクとオリーブオイルをフライパンに入れ、弱火でじっくり炒める(辛いのが好みの方はここで輪切りにした赤唐辛子を入れる)
- ニンニクの香りがでてきたら1のきのこを入れ、塩・ブラックペッパーをふり、しんなりするまで炒める
- やや濃いめの味付けに調整し、火から下ろして粗熱を取る
- 4をフードプロセッサーに入れてペースト状になったら完成
保存期間:清潔な密閉容器に入れて3日間ほど保存できます
きのこペーストを使ったアレンジ料理
- 牛乳200ccに「きのこペースト大さじ1」+「コンソメ小さじ1/2」を入れて加熱したら完成
- 一口大に切った鶏肉に塩コショウをし、しっかり火を通す
- 焼いた鶏肉にきのこペーストとチーズをのせ、チーズが溶けたら完成
- ピザ生地にきのこペーストをぬり、ベーコンとチーズをのせて焼いたら完成
とても簡単にできる料理ばかりなので、ぜひ作ってみてください。
作ったきのこペーストや料理の保存容器としておすすめなものは、食卓にそのまま出せる「iwaki(イワキ)ガラス製 保存容器」です♪
こちらの商品は、ガラス製で蓋を外せば食洗器で洗えます。
中身が見えるので、冷蔵庫の中でも探しやすく、食材の無駄をなくすことができますよ。蓋をしたまま電子レンジOK!外せばオーブン料理にも使えます。
まとめ


きのこが消化されない理由と改善方法がわかると、安心してきのこ料理を食べられますね。
いつでも手に入りやすく、栄養豊富なきのこは日々の食事に取り入れたいものです。調理のコツを参考にして、きのこ料理を楽しみましょう♪



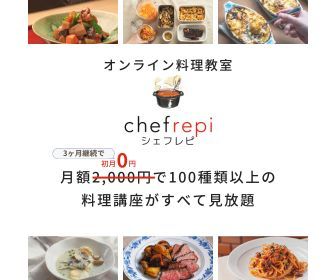
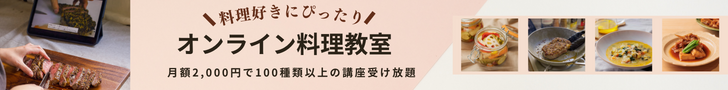


コメント