飲食店などにあるメニューはお店の第二の看板ともいえます。
メニューより味や接客に力を入れたほうがよいと思いがちですが、魅力的なメニュー作りにはお客様目線で考えることが欠かせません。
この記事を読むと、見やすいメニューを作ることができますよ♪
また、見やすいメニューでお客様にお店のイチオシメニューやセットメニューを選んでいただくと、注文数の管理に活用できます。
メニューを作ったら見やすい順にまとめたいですね。そこで、おすすめの商品として「メニューブックグレース」をご紹介しますね。
飲食店では水濡れなどでメニューが汚れてしまいやすいですよね。「メニューブックグレース」などの丈夫なファイルを活用すると、紙のメニューを管理しやすいですよ。
メニューのまとめ方も解説していますので参考にしてくださいね♪
見やすいメニューの作り方のポイント5つを解説!

 おもち
おもちどうして見やすいメニューが必要なの?
料理を注文するときに必ず見るメニューですが、このメニューがわかりにくかったり見づらかったりすると注文しにくく、店員の手間も増えてしまいます。
ひと目見て分かりやすく、おしゃれなメニューを見ると、料理が来る前から気分が上がるのではないでしょうか。
①写真をのせる
まずは、メニュー名と一緒においしそうな写真をのせましょう。
現代はSNSの影響もあり、普段から目で見る情報でものごとを決めることが多いのではないでしょうか。
ただメニュー名が並んでいるだけではどのような料理かわかりませんし、盛り付けられた写真があると料理やお店に対しての期待感も高まりますよね。
また、お客様がお店に満足してSNSなどで発信されるとお店の宣伝につながりますよ。
料理の写真を撮るときは、背景に店内などメニューの料理以外のものが写り込まないよう注意しましょう。
料理やドリンクをおいしそうに撮るには、光や方向がポイントですので、プロの方に写真を撮ってもらうのも良いですよ。
②レイアウトの仕方
デザインのレイアウトで大切な、「視線誘導」をメニューの作り方に利用すると良いですよ。
視線誘導とは、人が情報を見るときにストレスなく伝えることで、読みやすい順番を意識すると見やすいメニューになります。
チラシや雑誌などを見るときには、「左上」から「右下」に向かって見ることが多いといわれ、おもに「Zの法則」、「Fの法則」、「Nの法則」などがありますよ。
例えば、チラシや広告には左上から右下に目線が動く「Zの法則」、スマホなどのシンプルな記事には「Fの法則」、縦書きのものには「Nの法則」が活用されています。


そして、飲食店ではその店の注目してもらいたいメニューや、話題になるような看板メニューがありますよね。
看板メニューは他の定番メニューより大きくすると見やすくなり、お客様がより注文しやすくなりますよ。
また、メイン料理を目立たせて他のお店との違いや魅力を伝える効果もあります。
③メニュー名
メニューの名前はどうしたら見やすくなるのでしょうか。
ただ料理名が書いてあるだけではメニューの想像が難しいですよね。
そこで、メニューに「ホクホク」、「ゴロゴロ」、「シャキッと」などの擬音や、目を引く「〇〇産」などの名前をつけるとどんな料理が運ばれてくるかわかりやすいですよ。
また、人気のあるメニューや辛さなどがマークで示してあると選びやすくなるでしょう。
お店のコンセプトに合ったメニュー名ならお客様を惹きつけることができますよ。
④お店の雰囲気に合っているか
飲食店に限らず、お店にはそれぞれターゲットにしている客層やコンセプトがありますよね。
ファミリー向けにはにぎやかさ、若い女性向けにはパステル調などかわいらしさ、高級感を出したい場合は落ち着いた色調にするなど客層に合わせたデザインを考える必要があります。
狙った店の雰囲気とメニューの雰囲気がバラバラで、かみ合っていないと見やすいメニューとはいえません。
どういった雰囲気の店かがお客様に伝わると安心感がありますし、リピート率アップにもつながりますよ。
⑤お客様の立場にたっているか
見やすいメニューのポイントはお客様の気持ちで考えて作ることが大切です。
期間限定や1日◯食などと言われるとつい注文したくなりますよね。
そして、お店で食事をする際に値段がどれほどか気になりますよね。メニューと金額がはっきりわかるように記載することも大事なことですよ。
また、地域によっては外国からの観光客が多い地域や、外国人が多く住んでいる場所では外国語に対応したメニュー作りも考える必要があります。
外国語に対応できなくても、料理の写真でどんなメニューなのかを伝えることが可能ですので、やはり写真は大事ですね。
メニューを見るだけで注文可能であれば、店員が説明する手間をはぶくことができますよ。
見やすいメニューのデザインで気をつけることは?


見やすいメニューの作り方で大事なことは、お客様が見やすく、わかりやすいようにレイアウトすることです。
左上から右下へ読むように流れを作ることを意識すると見やすいメニューになりますよ。
文字のフォントや大きさ
お店のコンセプトや雰囲気に合ったフォントにすることも、メニューでお店のテーマを伝える効果があります。
しかし、読みにくいフォントや文字の大きさで読む気をなくしてしまっては意味がありませんので、見やすいフォントやサイズにすることも意識するとよいですね。
例えば、お客様に年配の方が多いなら文字のサイズを大きくする、子ども用のメニューにはひらがなで書いたりイラストを添えたりするなど、お客様がストレスなく読めるよう意識しましょう。
メニューブック
見やすいメニューを作ってもバラバラになってしまっては、お客様にとってわかりにくいメニューになってしまいます。
そこで、メニューの順番がバラバラにならないよう、ファイルなどを利用してメニューブックにまとめることがおすすめです。
まず、1ページ目はお店が注文して欲しい看板メニューやおすすめメニュー、限定メニューになります。1ページに載せるメニュー数は3〜5品が適切とされています。
1ページにメニューがたくさんあると読み飛ばされてしまいますので、特に目立たせたいメニューやメインメニューのページにはメニューの量を多くしすぎないように注意しましょう。
また、メニューブックのページ数は12ページ程度までにしましょう。それより多くなる場合は、ドリンクやデザート専用のメニューを別に用意すると良いですよ。
メニューをはさむものには、メニュー数が多い場合はメニューブック、メニュー数が少なめの場合や別に専用のメニューを用意する場合はパウチメニュー(ラミネート加工)がおすすめです。
メニューブックには高級感ある質感のものや、お店の雰囲気に合わせて準備した表紙をはさむことも可能ですので、用途やお店のコンセプトに合わせて使い分けをするのも良いですね。
見やすいメニューの店で満足度を高めよう!


ここまで見やすいメニューの作り方をご紹介してきました!
見やすいメニューには、たくさん工夫がされているので、自分の店にあった改善方法がみつかれば嬉しいです。
最後に見やすいメニューの店では、満足度がなぜ得られるのか解説していきますね。



メニューってたくさんのことを考えて作っているんだね
見やすいメニューを作ると、お店がおすすめするメニューをお客様に注文してもらいやすくなります。
メニュー表を見てすぐに目につく所にあるメニューは、つい注文したくなりますよね。
また、近くにセットメニューを配置することで、一緒に注文されることが多くなります。
その結果、お店としても商品コントロールができるようになりますよ。
そして、期間を定めたり季節によってメニューを変えたりすると、今お店が強化したいメニューを注文するよう誘導できます。
定期的にメニューが変わると、また違うメニューを試してみたくなりますのでリピート率アップにつながるでしょう。
また、お店がターゲットにしている客層に合わせてメニューのフォントを変えるなど、お客様にとって見やすいメニューの作り方ができるとよいですね。
まとめ


- 見やすいメニューの作り方は、お客様目線で考えることが大事
- 見やすいメニューの作り方は、「写真・レイアウト・メニュー名・お店の雰囲気・お役様の立場」5つのポイントがおすすめ
- レイアウトは、左上から右下へ見られる傾向があるので、「Zの法則」「Fの法則」「Nの法則」の3つが重要
- メニュー名では、「擬音」や「〇〇産」などを書き、わかりやすさやインパクトを与えるが大事
- 見やすいメニューのデザインは、文字のフォントや大きさに気をつける
- お店がターゲットにしている客層を意識する
- メニューがバラバラになってしまうのを防ぐためにメニューブックがおすすめ
メニューがわかりにくいために注文に手間取ってしまうと、お客様はお店にネガティブな印象を持ってしまいます。
せっかく料理の味や接客が良くても、ひとつのネガティブな印象でお客様を逃してしまってはもったいないですよね。
見やすいメニューの作り方を知ることで、お客様のことを考えたお店づくりができますのでぜひ参考にしてみてくださいね。




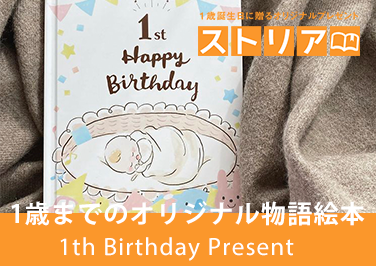

コメント