厄年に結婚をしても大丈夫です!「役年」ともいわれ縁起がよいともされていますよ。
厄年に結婚をすることになってしまい、本当に大丈夫なのかなと心配になりますよね。
実際に私は、入籍はギリギリ厄年ではありませんでしたが、コロナの影響もあり結婚式は延期になってしまい、厄年にすることになってしまいました。実体験も踏まえて、解説していきますね!
厄年は勘違いされているかたも多いですが、本当の意味は「身体や環境の変化がある年なので気をつけなさい」という年です。
きちんと理解すると心配も薄れていくので、詳しく解説していきますね。
厄年でも心をスッキリさせて幸せな結婚に進みましょう!
男性・女性の厄年や、高齢の厄年も紹介しますので最後までお見逃しなく♪
厄年に結婚をしても大丈夫な理由
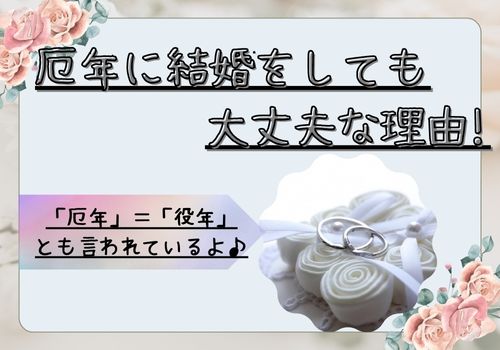
厄年に結婚しても大丈夫な理由は、「役年」ともいわれているからです。「役年」とは何か後ほどご紹介しますね。
まずは、厄年の本当の意味を理解していきましょう。
基礎知識から勘違いをしている厄年の情報まで解説していきます。
厄年の基礎知識
厄年は自分の環境や身体などが変わりやすく、気をつけなければいけない年齢です。
昔から年齢的にも家庭や仕事などで色々な物事が起きて、身体に疲労がでやすくなるので、特に注意が必要な年だという知恵でもありますよ。
平安時代に厄年という考え方はあったそうですが、風習の一つであり科学的根拠はないそうです。
ですので、身体に変化が起きる年なので気をつけていれば、厄年に結婚しても大丈夫ですよ。
厄年の勘違い
「厄年は悪いことが起きる」「災害に見舞われてしまう」などと思っている方が多いですが、迷信です。
実際は、身体の不調や環境の変化がある年なので気をつけましょうという意味ですよ。
ですので、全てを厄年のせいにせずに、新しい環境に慣れたり、自分の新たな出発だと思ったりすれば、将来自分の起点になったということにもなります。
例え厄年ではなくても悪いことも良いこともありますよ。厄年という観点にとらわれず、1日1日を大切に過ごしていくことに専念しましょう。
また、「役年」ともいわれ、家庭ではこれから増えていく家族のため、仕事では今まで頑張り積み重ねた実績を活かし、会社や社員のためなど自分が役に立つことができる年ともいわれています。
「役年」と考えれば、結婚するタイミングにはよい意味ですね♪
厄年の数え方とは
厄年の数え方はよく間違ってしまうのが、そのまま今年の実年齢で見てしまうことです。
厄年は数え年と言われていて、自分が生まれた年に「1歳プラスした数」ですよ。
例えば、平成元年の生まれだった場合、実年齢は34歳(2023年時点)ですが、数え年だと35歳になるのです。
厄年と言えば「前厄」「本厄」「後厄」と3年続きます。では、女性の厄年について見ていきましょう!
女性の厄年
女性の厄年を見ると、なんと本厄が4回もあります。(数え年で19歳、33歳、37歳、61歳)
その中でも「大厄」と呼ばれる年は「33歳」ですので気をつけましょう!
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
男性の厄年
男性の厄年を見ると本厄は3回で、女性より少ないですね。(数え年で25歳、42歳、61歳)
その中でも「大厄」と呼ばれる年は「42歳」ですので気をつけましょう!
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| 60歳 | 61歳 | 62歳 |
しかし、ここで注意しなければいけないことがあります。
代表的な年齢までしか公表されていないことが多いですが、実は「高齢の厄年」があり、続きがあるので注意しなければいけません。
自分は終わったと思っていたら、実は本厄でしたなんてこともありますよ!
62歳の厄年を終えたとホッとしている数年後に、運気もなくおかしいとなり神社に聞きに行くと「今年あなた厄年ですよ」と言われ、そのまま祈祷することにもなりかねません・・・。
終わったと思わず、気をつけることを心がけましょう!
高齢の厄年
男女ともに長寿の祝いを迎えた年の「翌年」といわれています。(古希70歳、喜寿77歳、傘寿80歳、米寿88歳、卒寿90歳)
高齢の厄年は、71歳、78歳、81歳、89歳、91歳です。
厄年の結婚は厄落としをしてスッキリ迎えよう!

「厄払い」「厄落とし」「厄除け」など1度は耳にしたことがありますよね。
同じような響きですが、意味が違うのでここではそれぞれ解説していきます。
厄払いに行くときの注意点も一緒にご紹介しますね。
厄落とし
「厄落とし」とはこれから災厄が来ないように、先に厄を作成し、その厄を落とすことです。
一瞬どういう意味なのか疑問ですが、昔は自分がいつも使用している物に厄をうつし、自分の厄を落としたとされていました。
しかし、厄落としのやり方は地域によっても違いがあるので近隣の神社やお寺に聞いてみるとよいですね。
厄払い
「厄払い」とは、自分に既についてしまっている厄を払うために神社で祈祷をしてもらうことです。
私は心配性なので厄年の3年間は、毎年1月の末までに厄払いの祈祷に行っていました。
本来は、本厄の年に祈祷してもらうのが一般的だそうです。
厄払いは、2月の節分までにすませたほうがよいとされていますが、地域や神社によっては1月末までと決まりもあるので行く前には確認した方が安心ですよ。
厄払いの注意
【服装】
男性はスーツやフォーマルな服、女性は落ち着きのあるワンピースやフォーマルな服を選ぶとよいですよ。
あまりに派手な服装だと、他のかたに冷たい目で見られることもあるので注意です。
神様にお願いするので、それなりにしっかりとした服装を心がけましょう。
【金額】
相場は、5千円~1万が多いです。(神社によって相場が違うので確認しましょう。)
「5千円~」という表記をよく見かけますが、いくら払えばよいのかと迷ってしまいますよね。
そんなときは最低限の5千円を払えば、神社のかたも悪く思わず受け取ってくれますよ。
ただ注意が必要なのが1つの祈祷につきなので、もし他の祈祷もお願いするときには単純に倍の金額をお支払いしなければいけません。
【時間】
おおよそ10~15分ほどで終わります。ただし、お正月には祈祷も多く待ち時間は長いこともあります。
途中からの参加はできない場合が多いので時間は厳守ですね。
【子供】
さまざまな祈祷のかたが来られるので、お子さんの祈祷でない場合は祈祷しないかたに預けていくのが無難です。
なかには子供が途中で騒いでしまって全く神主さんの声が聞こえないこともあり、集中できないと怒られる方もいますよ。
厄除け
厄除けは、既についている厄を払うのではなく、これからつく厄を除けるという意味で、予防する効果があります。厄除けをする場所は寺院です。
まぎらわしいですが、「厄払い」は神社で祈祷、「厄除け」は寺院で祈祷しますよ!
厄年に注意するべきポイント7選
これで厄年に結婚してもよいと安心されたと思います。
次に結婚後に起こりえる出来事で抜けてしまいがちな、厄年で注意するポイントを解説していきますね。
1.新婚旅行は海外を避けたほうがよい

新婚旅行というと海外を想像する方も少なくないですが、身体のエネルギーが不足しがちな厄年に行くと、体力もないのでトラブルに巻き込まれることも・・・。
海外の環境に慣れていなくいつも以上に体調を崩してしまうこともあります。なるべく大きな移動は避けたいですね。
2.新しく家を建てるのは避けたほうがよい

結婚をすると次に新居を建てたり、マンションを購入したりとしたくなりますよね。
しかし、厄年では判断力が鈍るので、しっかり決めたはずが見落としがでて後悔してしまうなんてこともありますよ。
私も後厄に建ててしまったのもあってか、引き渡し後にトラブルは色々ありました。
どうしてもこのタイミングで建てなければいけないこともあるので、そんなときは神社などに祈祷しにいくとよいですよ。
私は鬼門封じをお願いして、お札を鬼門・裏鬼門にあたる場所に貼っています。
3.転職は避けたほうがよい

結婚を機に家族が増えて守るものができたので、収入を増やしたり、自分のステップアップのために転職する方がいます。
しかし、環境の変化には厄年は向いていないので、避けることをおすすめしますよ。
収入が増えても人間関係がうまくいかず、仕事を辞めることになることもあります。
厄年の間は現状維持がベストなので、転職するのは過ぎてからがよいとされますよ。
4.部屋の整理整頓をしたほうがよい

厄年に新しい物を購入するのはあまりよくないと言われていますが、捨てるにはもってこいの年ですよ。
この機会に断捨離をしましょう。いらない物が多いと部屋も片付かず、整理整頓ができません。
捨てることによりお部屋にも余裕がでてきて、整理整頓をすることで気持ちもスッキリとしますよ。
5.食生活に注意したほうがよい

厄年は身体の不調が起きやすいので、食生活には注意が必要です。
栄養バランスをしっかりとし、女性は特に出産の時期と重なるかたが多いので、自分の食生活を見直す必要があります。
厄年は勉強に取り組むとよい年なので、栄養素など詳しく調べてみるのもおすすめですよ。
6.毎日掃除をしたほうがよい

毎日掃除をすることで悪い気がたまりにくくなり、常に新しいよい気が流れてきます。
全部のお部屋を掃除するのは大変なので、毎日ここはやるなど決めて少しずつで大丈夫ですよ。
水場は特にたまりやすいので、念入りにするとベストです。
7.夫婦でホッと一息つく時間を作ったほうがよい

悪いことが続き、全て厄年のせいにしてしまうと夫婦で喧嘩が増え、お互いを責め合ってしまいます。
不安定になり、イライラすることもありますが、ここではゆっくりと夫婦でお互いに何を思っているかなど落ち着いて話し合ってみてはいかがでしょうか。
近くのパン屋さんにあるテラスでのんびり朝食を食べるなど、ほんの些細なことでもよいのでゆっくりとできる時間を作ると夫婦の仲も深まります。
心に余裕がないとお互いにイライラして、喧嘩になってしまうので、時間がなく忙しいかたでも厄年には特にホッとできる時間を作るよう心がけましょう。
厄年の結婚や入籍は意味がわかれば安心する
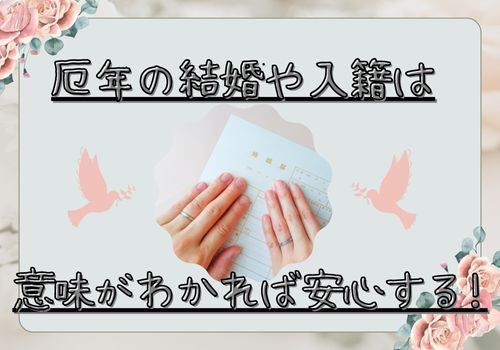
よく厄年に入籍、結婚はしない方がよいと耳にしますが、実際には厄年でも大丈夫です。
厄年ということにとらわれるよりも、自分の入籍や結婚するタイミングを逃さないことが大事ですよ。
そうは言っても気になる気持ちはよくわかります。できれば避けたいなと思いますよね。
確かに私も厄年にあたったので、結婚式をしても大丈夫なのかと心配になった経験があります。神社に確認しに行ったこともありました(笑)
まず自分の目の前に起きている現実と厄年を天秤にかけたとき、どちらが大切なのかを考えていきましょう。
厄年だからと今年入籍を先延ばしにしたら、せっかくのタイミングを逃してしまうこともありますよ。
まずは自分がベストタイミングであるなら、自分の人生に悔いが残らないよう、決断しましょう。
厄年の結婚や出産は縁起がよい!?
.jpg)
結婚をしたら次は子供が欲しいと思うかたは多いですよね。
厄年に結婚することは大丈夫ですが、「出産」することは縁起が悪いと聞いたことはありませんか。
例えば「子供に厄がうつる」など不吉な言葉を聞いたことがあるかたもいますよね。
実際に厄年に結婚して出産がよくないのか解説していきます。
厄年に出産すると縁起がよい!?
地域や宗教などで少し意味が異なることもありますが、厄年の出産により、赤ちゃんが母体の厄を払ってくれると思われることが多いようです。
しかし、ここで注意することが1点あります。実は、男女によって意味が変わってきてしまうということです。
昔から男の子は将来家の大黒柱になるという考えから、厄を払ってくれたと解釈されたようですね。
一方、女の子は「厄がうつる」と言われることもあったそうです。
しかし、どちらも明確な根拠はないのでもし子供が女の子でも母子ともに元気でいることが一番大事なので深く考えすぎないようにしましょう。
無病息災の儀式(捨て子の儀式)
厄年に女の子が生まれたときに、厄をうつさないためにする儀式です。
捨て子の儀式ともいわれていますが、本当に捨てるという意味ではないので安心してください。
※こちらは絶対にしなければいけない儀式ではないので、気になってしまうかたは近隣の神社などで詳しく聞いてみるとよいですよ。
- 近隣の神社に相談しにいく(赤ちゃんを一晩預かってくれるかた(親族など)を探しておく。いない場合は神社の神主さんに相談)
- 日どりを決めて、再度赤ちゃんを預かってもらうかたと来る
- 当日、神社に赤ちゃんを預かってもらうかたは待機してもらう
- 赤ちゃんを神社に連れていき、神社に捨てるふりをする(カゴなどあるか確認)そのまま両親は振り返らずに帰宅
- 待機してもらっていた親族に赤ちゃんをすぐに拾ってもらい、一晩預かってもらう
- 翌日赤ちゃんにお祝いの服を着せて、両親に返す
こちらは古くから伝わる風習ですが、赤ちゃんは「もらい子」になるので、厄を落としたことになるようです。
しかし、この儀式を行わなくても厄が赤ちゃんにうつるということはないので、深く考えずに母子の健康を第一に考えていきましょう。
赤ちゃんが生まれるということは本当に奇跡に近いことです。
まずは誕生してくれたことをお祝いしてあげましょう♪
まとめ

- 厄年に結婚、入籍しても「役年」ともいわれるので大丈夫
- 厄年は自分の環境、身体などが変化しやすい年齢のこと
- 女性の厄年は数え年で19歳、33歳、37歳、61歳
- 男性の厄年は数え年で25歳、42歳、61歳
- 高齢の厄年は、男女ともに71歳、78歳、81歳、89歳、91歳
- 厄払いは神社で、厄除けは寺院で祈祷する
- 厄年に出産しても深く考えず、母子の健康を優先する
厄年に結婚をしても自分のベストタイミングなら大丈夫です!
厄年は気にしてしまいがちですが、それだけのために大事な結婚を逃してしまうのはもったいないですよ。
厄年にとらわれず、お互いの気持ちを大切にして、幸せな結婚ができることを願っています♪


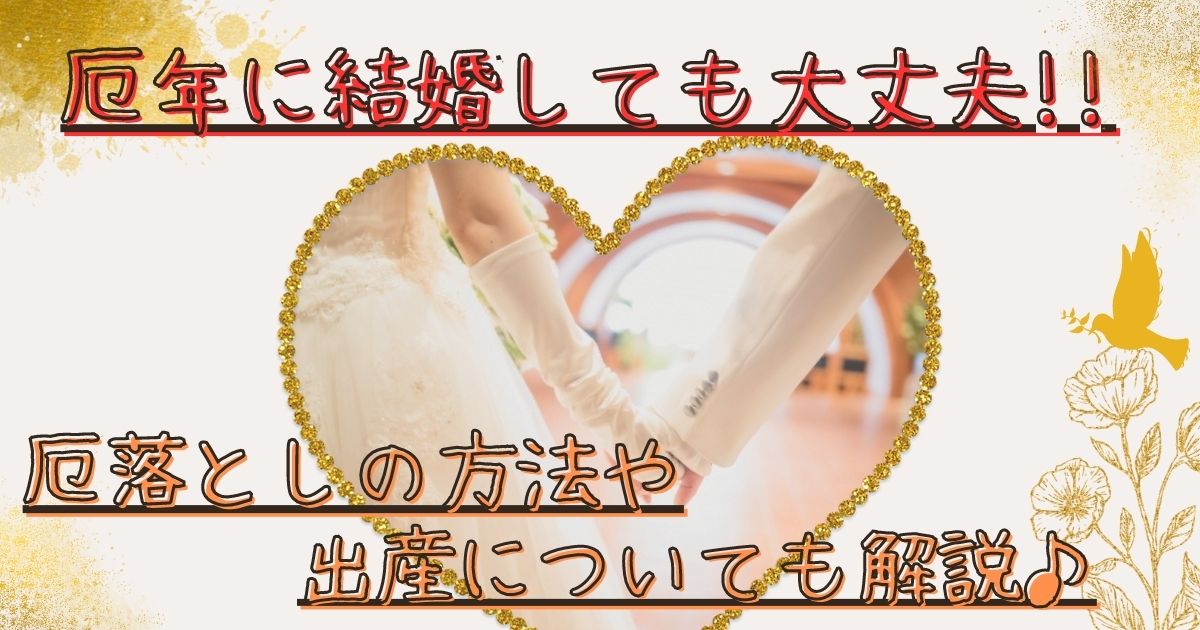




コメント